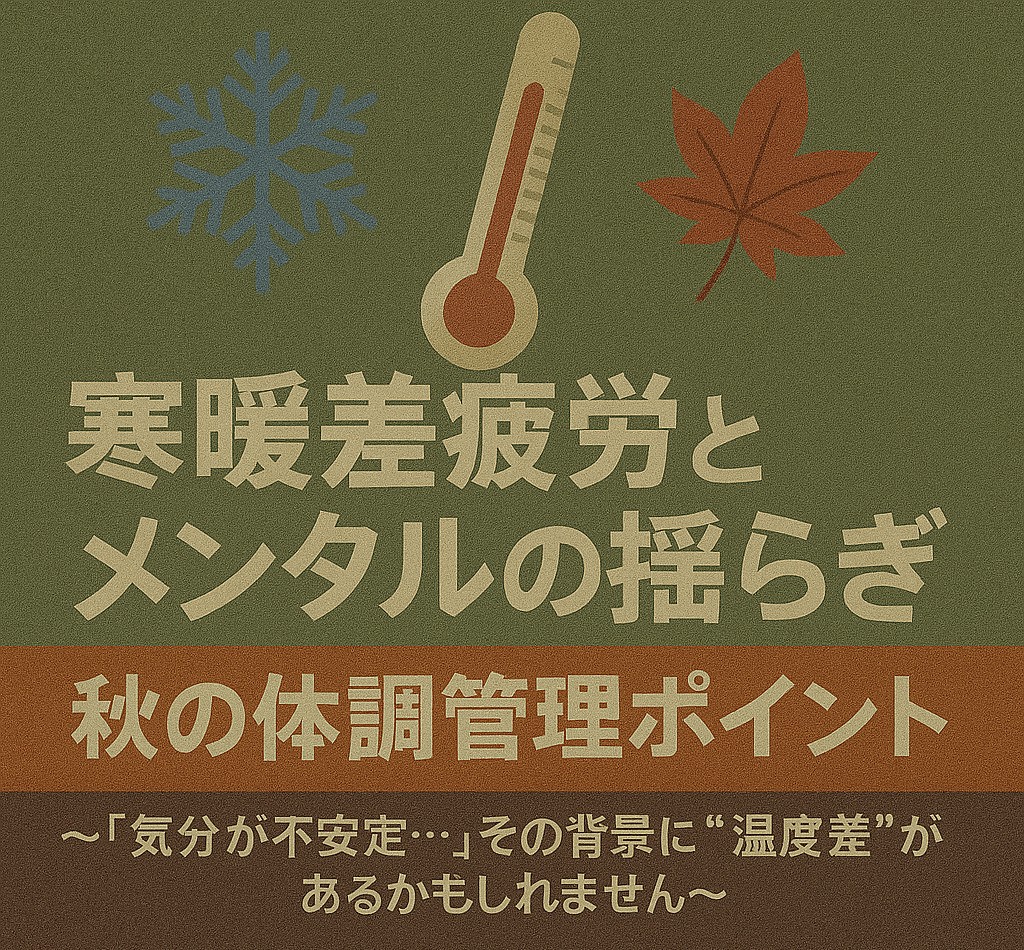~「気分が不安定…」その背景に温度差があるかもしれません~
はじめに
朝晩の冷え込みと、日中のポカポカ陽気、10月は、一日の中でも気温差が大きくなる季節です。
この寒暖差は、実は私たちの自律神経に負担をかけ、心と体に影響を及ぼす要因のひとつです。
精神疾患をお持ちの方にとっては、「なんとなく不安」「疲れが抜けない」「気分が落ち込みやすい」といった症状が、この時期に強まることもあります。
この記事では、寒暖差が引き起こす“寒暖差疲労”とメンタルへの影響、そして訪問看護や日常でできる対策についてご紹介します。
寒暖差疲労とは?
寒暖差疲労とは、日中と朝晩の気温差に体がうまく対応できず、自律神経が疲れてしまう状態を指します。
◆ 秋の典型的な症状
- 疲れやすい
- 頭痛・肩こり・めまい
- 不安感やイライラ、気分の落ち込み
- 睡眠の質の低下(中途覚醒・寝つきの悪さ)
特に10月は、夏から冬への「季節のはざま」にあり、身体が環境に適応しきれないまま疲労が蓄積しやすい時期です。
自律神経とメンタルの関係
自律神経は、呼吸・血圧・体温・消化などを調整する働きがあると同時に、感情の安定や精神状態とも深く関係しています。
寒暖差によって交感神経と副交感神経の切り替えが乱れると、
- 「体が休まらない」
- 「頭がさえて眠れない」
- 「ちょっとしたことで不安定になる」
といったメンタルの揺らぎが起こりやすくなります。
訪問看護の現場でよく見られる変化
- 「寝ても疲れが取れない」
- 「日中ぼーっとして動き出せない」
- 「涼しくなってから、気分が沈みがちになってきた」
- 「朝夕になると不安が強まる」
こうした声が10月に増えることは珍しくありません。
だからこそ、体調の揺らぎを気持ちのせいではなく季節のせいと捉える視点が大切になります。
セルフケアと支援のポイント
1. 服装の調整で体温を守る
- 薄手の上着・ストール・レッグウォーマーなど、こまめな温度調整ができる服装を
- 足元や首元を冷やさない工夫が、自律神経の安定にもつながります
2. 朝の光を浴びて体内リズムを整える
- 起床後すぐにカーテンを開けて光を取り入れる
- 外に出られない日も、室内で明るく過ごすだけでセロトニン(幸福ホルモン)の分泌を促せます
3. 食事と水分補給で内側から整える
- ビタミンB群・マグネシウム・鉄分を意識(例:納豆、卵、バナナ、海藻、豆腐など)
- 夏と違って喉の渇きを感じにくくなるため、意識的な水分補給(常温がおすすめ)を忘れずに
4. 軽い運動と深呼吸で自律神経をサポート
- 無理のない範囲で、散歩・ストレッチ・ラジオ体操などの軽い運動を
- 寝る前に腹式呼吸を行うことで、心身の緊張をゆるめる効果も期待できます
訪問看護でできる関わり方
- 服装や室温、飲食の傾向など、季節の変化に合った生活スタイルになっているかチェック
- 「最近よく眠れていますか?」「疲れが取れていますか?」と、気分だけでなく体調にフォーカスした声かけ
- 必要に応じて、主治医やご家族と気分変動や日常生活への影響を共有
まとめ
寒暖差による心身の疲労は、誰にでも起こりうる自然な反応です。
特にメンタルに不調を抱える方にとっては、ちょっとした気候の変化が大きなストレスになることもあります。
大切なのは、「なんとなく調子が悪い」の背景にある季節のサインに気づくこと。
訪問看護ステーションharu style・グループホームなつでは、その気づきをきっかけに、その人らしいリズムと安心を取り戻す支援を心がけていきたいと思います。
![精神科看護特化型 訪問看護ステーション haru style [ハル スタイル]|茨城県土浦市、かすみがうら市、つくば市、牛久市、阿見町、石岡市、竜ケ崎市](https://haru-style.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-haru_logo.png)