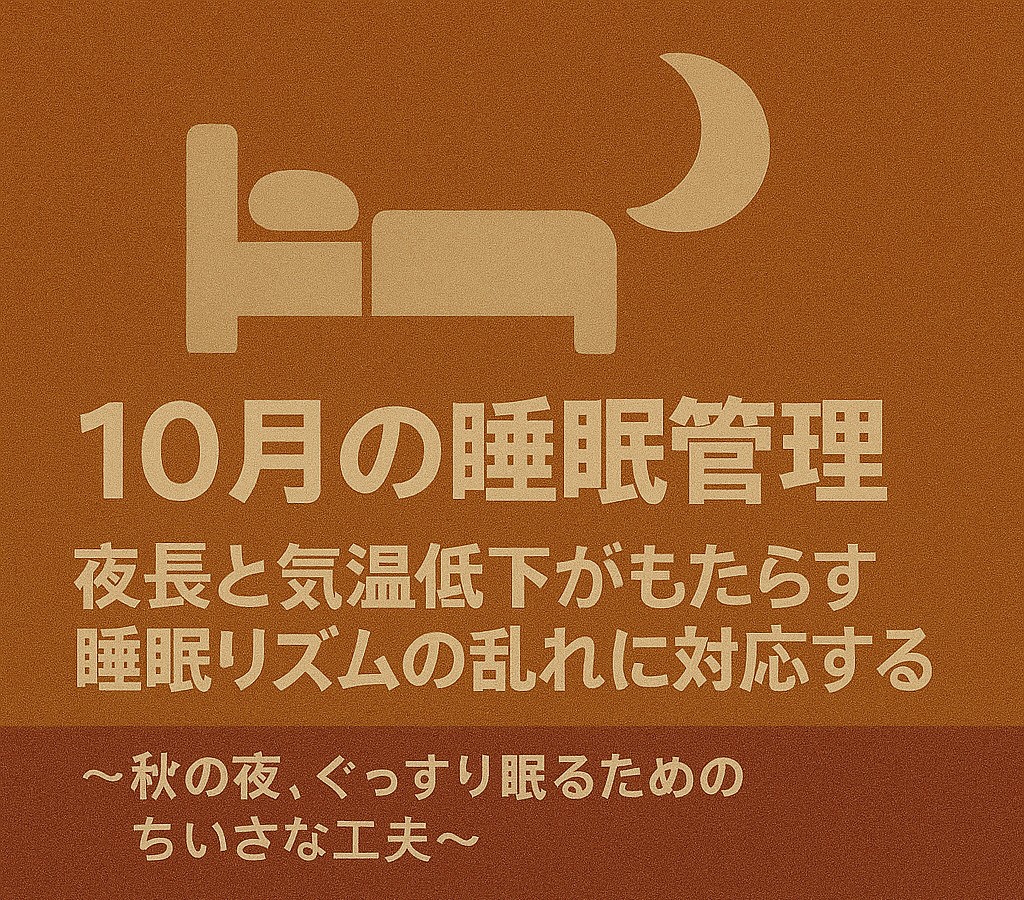~秋の夜、ぐっすり眠るためのちいさな工夫~
はじめに
10月は「秋の夜長」とも言われ、ゆったりとした夜の時間を楽しめる季節ですが、
同時に「なぜか寝つけない」「夜中に目が覚める」「朝がつらい」といった睡眠の乱れが目立つ時期でもあります。
その原因の一つは、気温の低下や日照時間の変化によって体内リズムが乱れやすくなること。
特に精神疾患をお持ちの方にとっては、こうした変化が生活全体のバランスや気分の安定にも影響するため、早めの対策が大切です。
この記事では、10月に起こりやすい睡眠の乱れと、その改善策について、照明・就寝前の習慣・服装など、実践的なポイントをご紹介します。
秋に起こりやすい睡眠トラブルとは?
1. 昼夜の気温差による体温調節の乱れ
- 日中は暖かいのに、夜は急に冷え込むこの寒暖差が、体のリズムを乱し、自律神経を刺激します。
- 結果として「寝つきにくい」「夜中に寒くて目が覚める」「朝スッキリ起きられない」といった不調が起こりやすくなります。
2. 日照時間の減少によるメラトニン分泌の乱れ
- メラトニン(睡眠ホルモン)は暗くなることで分泌が始まるため、
日の入りが早まる秋は、夕方以降の眠気が強くなったり、逆に夜間の覚醒が続いたりとリズムの乱れにつながることがあります。
3. 「夜が長いこと」による心理的影響
- 静かな夜の時間が増えることで、考えごとや不安が強くなる傾向も。
- 特にうつ病や不安障害の方では、夜間の過覚醒(神経が高ぶって眠れない状態)が顕著になることもあります。
睡眠リズムを整えるための3つの工夫
1. 【照明】朝と夜の光環境を見直す
- 起床後はすぐにカーテンを開けて自然光を浴びる
- 曇りの日や室内が暗い場合は、白色ライトや光目覚まし時計を活用するのもおすすめ
- 就寝1時間前には暖色系の間接照明や常夜灯に切り替えて、脳を夜モードに
2. 【習慣】就寝前の「おやすみルーティン」をつくる
- 例:白湯を飲む → ストレッチ → 好きな音楽をかける → 明かりを落とす
- 毎日同じパターンを繰り返すことで、これをすると眠る時間という意識づけが自然とできるように
- 就寝前のスマホやテレビは、なるべく控えてブルーライトをカット
3. 【服装・寝具】寒暖差を防ぐ秋仕様への調整
- パジャマは吸湿性・保温性のある長袖・長ズボンを基本に
- 足元や首回りを冷やさないよう、靴下・ネックウォーマー・薄手毛布の併用も◎
- 寝具は通気性と保温性のバランスが取れたものに切り替えを。夏用シーツのままでは冷えの原因に。
訪問看護での支援のヒント
- 「最近、夜はぐっすり眠れていますか?」と睡眠の状態を気軽に確認する
- 睡眠日誌の記録を勧めることで、リズムの乱れや寝つきの傾向を把握しやすくなる
- ご本人の安心スイッチ(お気に入りの毛布・香り・音楽など)を確認して、入眠ルーティンのサポートにつなげる
- 必要に応じて、主治医に相談して服薬のタイミングや種類の調整も検討
ご家族・支援者へのアドバイス
- 睡眠に関する悩みは気づきにくく、話しにくいテーマであるため、
「夜中に起きていないか」「表情に疲れが出ていないか」といった生活の中での観察が大切 - 寝具の状態や室温を一緒に確認し、「これでいいのかな?」と一緒に試行錯誤する姿勢を持つことも、支えになります
まとめ
10月は、気温・光・心理的な環境が大きく変化する季節です。
こうした「目には見えにくい変化」が、睡眠という生活の土台に静かに影響を与えることを知っておくことが、メンタルケアの第一歩になります。
「眠れていますか?」という何気ない問いかけから、その人に合った生活リズムや安心できる就寝環境づくりを一緒に考えていくことが大切です。
![精神科看護特化型 訪問看護ステーション haru style [ハル スタイル]|茨城県土浦市、かすみがうら市、つくば市、牛久市、阿見町、石岡市、竜ケ崎市](https://haru-style.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-haru_logo.png)