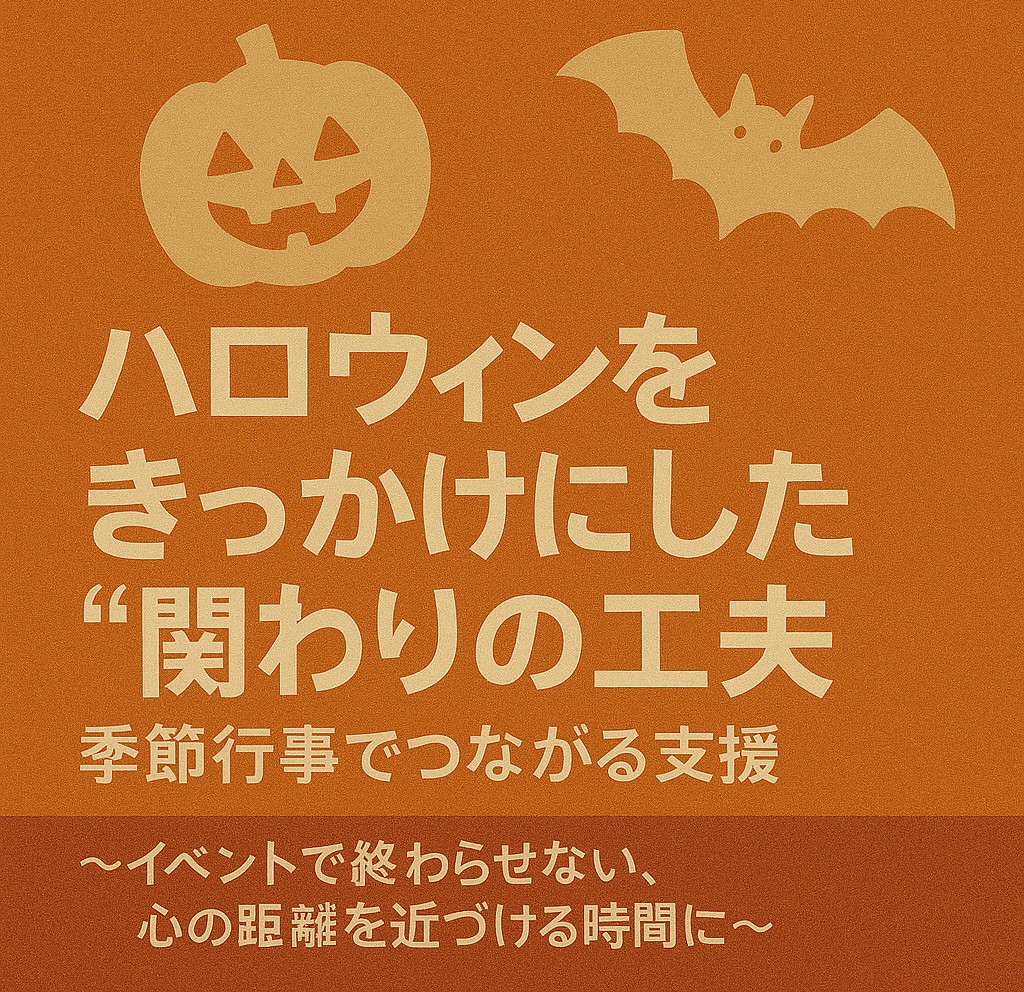~「イベント」で終わらせない、心の距離を近づける時間に~
はじめに
近年、日本でもすっかり定着したハロウィン。
「仮装」や「お菓子」「飾り付け」など、視覚的にも楽しいイベントとして、多くの施設や家庭でも取り入れられるようになってきました。
しかし、ハロウィンはただの年中行事にとどまらず、利用者の感情表現や人とのつながり、季節感を取り戻すきっかけとしても有効です。
今回は、訪問看護の現場でも気軽に取り入れられる、ハロウィンを心の交流ツールとして活かす支援アイデアをご紹介します。
ハロウィンを活用する意義とは?
1. 「季節を感じる」ことで生活に彩りが生まれる
- 日々の生活に季節感を取り入れることは、時間の流れや社会とのつながりを実感する手段となります。
- 秋の行事としてのハロウィンは、色や形・においなどを通して、五感を刺激するきっかけにもなります。
2. 気軽に楽しめる「非日常」体験
- ちょっとした飾りや小道具で、いつもと違う体験を共有できるハロウィンは、利用者の好奇心や会話を引き出しやすい機会です。
- 特に、ルーティンが強い方や人と関わることが苦手な方にとって、自然な形で交流が生まれる可能性があります。
訪問看護でのハロウィン支援アイデア
1. 【飾り付け支援】視覚で楽しむ空間づくり
- かぼちゃやおばけ、コウモリなどのモチーフを使った折り紙・ちぎり絵・ぬり絵を一緒に作成
- ご本人のお部屋に小さなハロウィン飾りを一緒に置くことで、季節感と達成感を得られる
- 「この色が好き」「ここに飾ろうか」といった会話のきっかけ作りにも
2. 【仮装・小道具活用】非日常で心の開放を促す
- フル仮装でなくてもOK。カチューシャ・帽子・マント・シールなどの小物で十分雰囲気を楽しめます
- ご本人にも無理なく、「これ、つけてみませんか?」「一緒に写真を撮りましょうか?」と軽やかな提案を
- 職員が仮装して訪問するだけでも笑顔が生まれやすくなります
3. 【お菓子づくり・食支援】五感で楽しむ関わり
- 市販のお菓子に手作りのラッピングを加えるだけで特別感がアップ
- クッキーにかぼちゃ型のスタンプを押す・チョコペンで顔を描くなど、創作+味覚で喜びを共有
- 嚥下や食事制限がある方には、ゼリーやプリンなど個別に配慮した工夫を
支援のポイント:大切なのは「一緒に楽しむ」こと
- 「完成させること」や「上手に作ること」よりも、過程を共有することに意味があります
- ご本人が関わりを拒む場合でも、無理強いせず、見る・聞く・触れるだけでもOK
- ハロウィンをきっかけとして、普段とは少し違う自分を楽しめる空間づくりを心がけましょう
ご家族・支援者との連携も効果的
- ご家族に「少しだけ飾りつけを一緒にしてみませんか?」と声をかけることで、家庭内のコミュニケーションが広がる
- 支援者同士で「この飾りがよかった」「〇〇さんが笑ってくれた」など、活動の成功体験を共有することが次の工夫につながります
まとめ
ハロウィンは、笑顔と変化を自然に引き出す力のあるイベントです。
その魅力を活かして、利用者の方にとっての「気分転換」「表現の場」「つながりの入り口」となるような支援を、訪問看護の中でもぜひ取り入れてみましょう。
派手なイベントでなくてかまいません。
小さなきっかけから始まる対話や笑顔の積み重ねが、安心や自信の芽を育ててくれます。
![精神科看護特化型 訪問看護ステーション haru style [ハル スタイル]|茨城県土浦市、かすみがうら市、つくば市、牛久市、阿見町、石岡市、竜ケ崎市](https://haru-style.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-haru_logo.png)