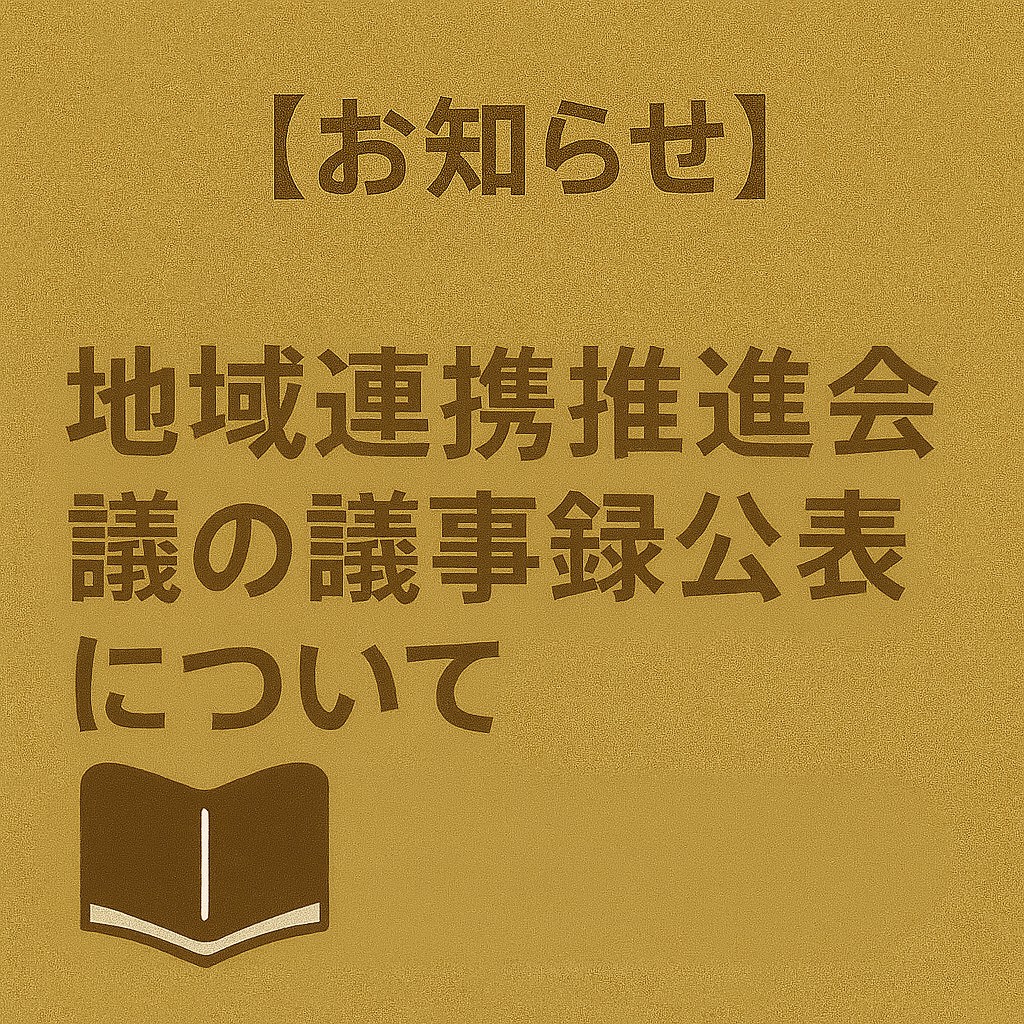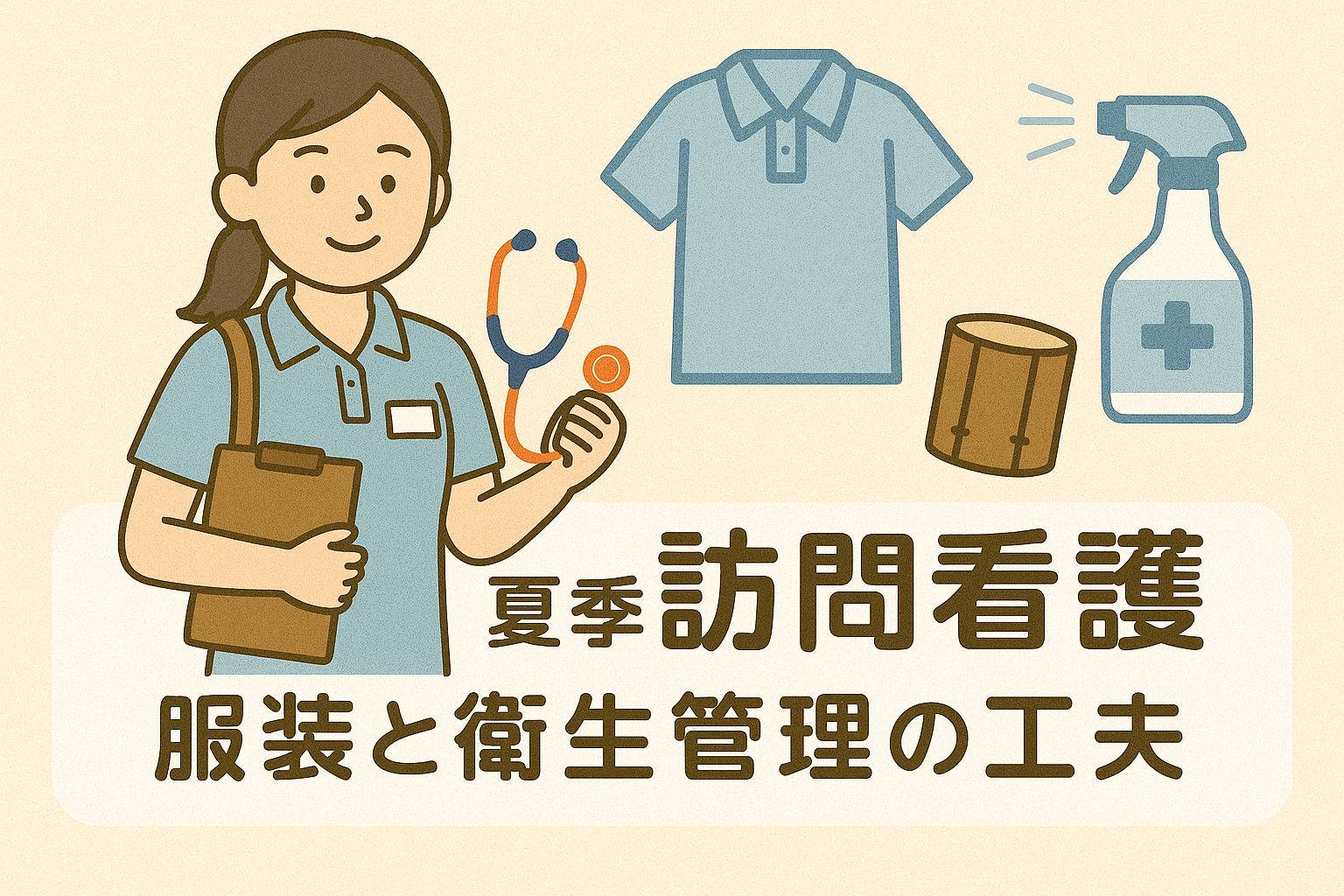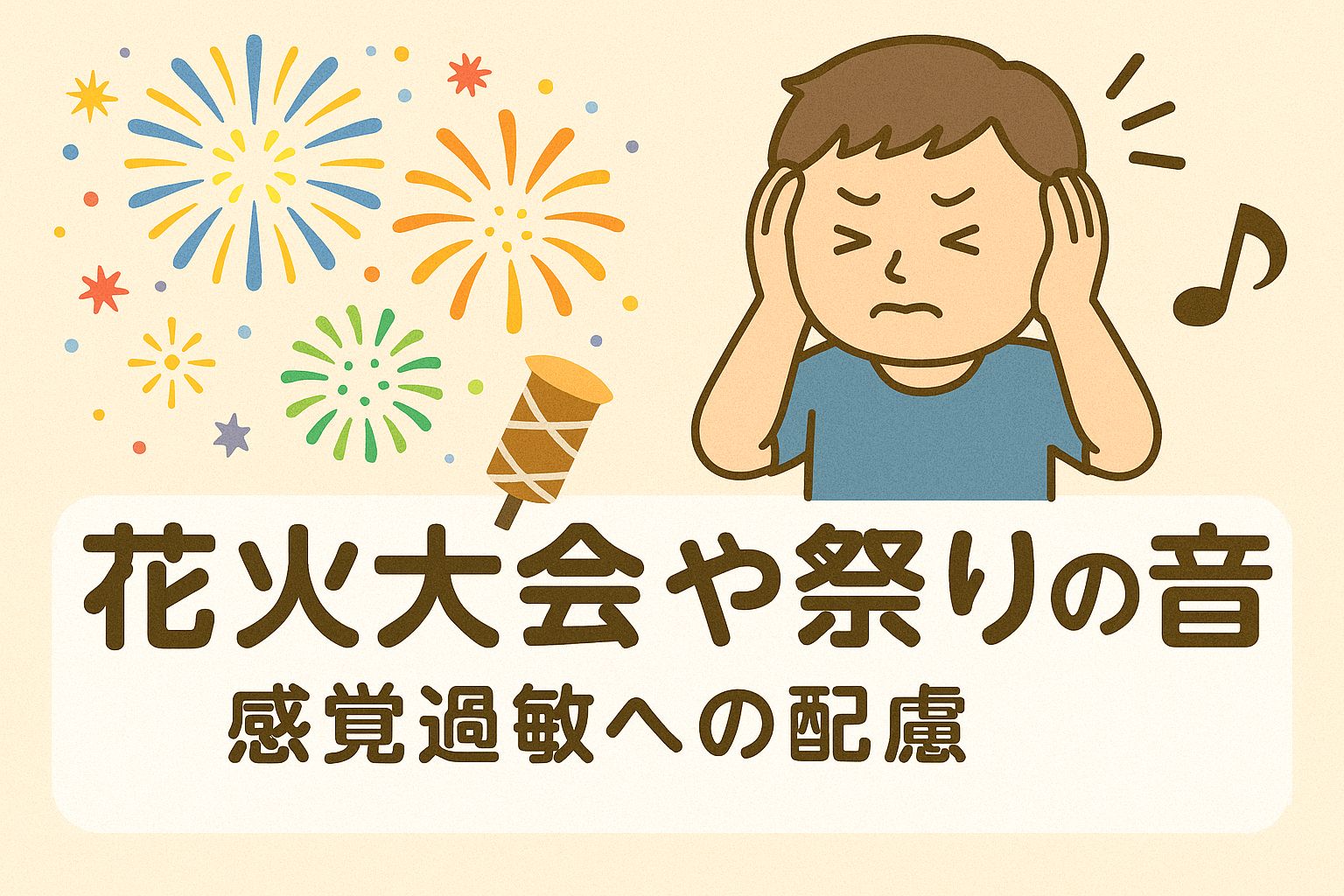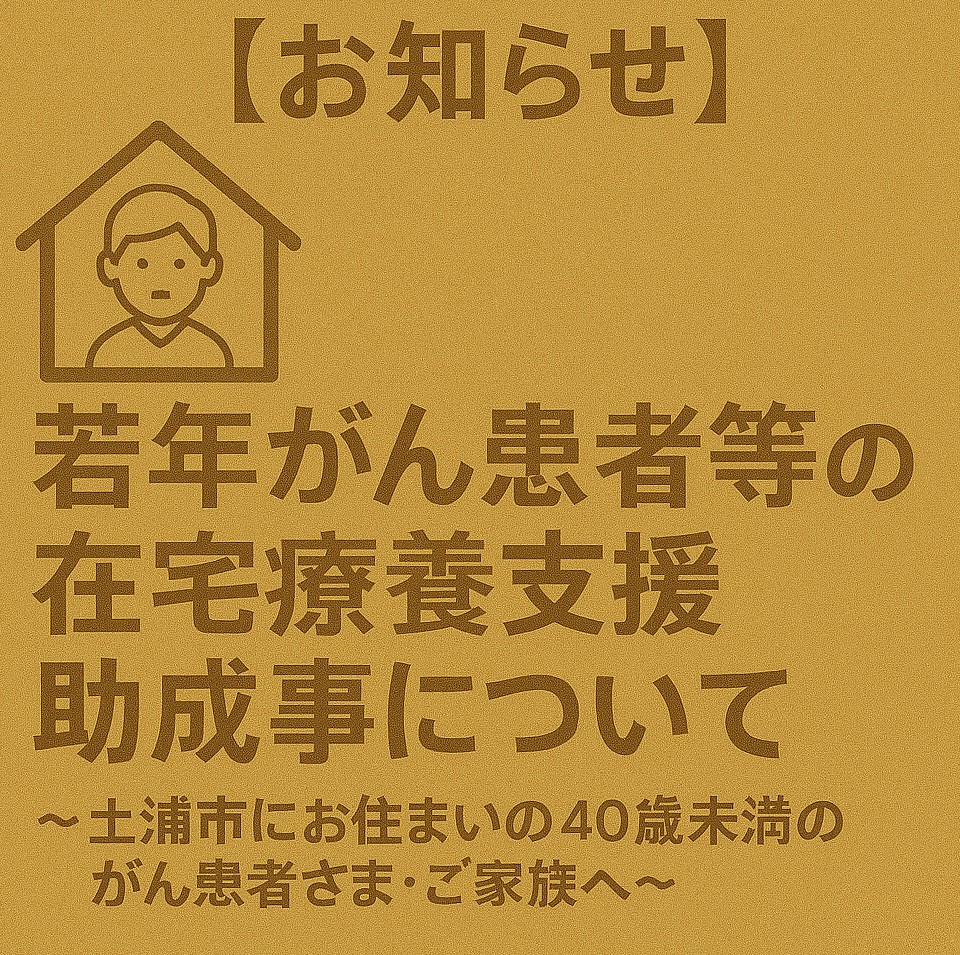令和7年8月12日(火)に地域連携推進会議を実施しました。
内容につきましては、議事録を載せましたのでご確認下さい。
宜しくお願い致します。
夏の夕暮れと気分変動:日照時間と気分の“揺れ”にどう向き合うか
〜「なぜか切ない」「落ち着かない」その感情には理由があります〜
はじめに
夏の夕方――少し涼しくなってホッとする反面、「なんとなく切ない」「落ち着かない」「急に不安になる」と感じる方が増える時期でもあります。
特に精神疾患をお持ちの方にとっては、夕暮れという時間帯が気分変動や不調の引き金になることもあります。
この記事では、「夏の夕暮れがもたらす心理的影響」と「その時間帯にできる対応やサポートの工夫」について、精神科訪問看護の視点からご紹介します。
なぜ、夏の夕暮れは“気分が揺れる”のか?
1. 日照時間の変化と体内リズム
- 夏は日照時間が長く、夕方になっても明るさが続くことで、脳内の「時間感覚」がずれやすくなります。
- 日が沈むとともに分泌されるメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が遅れ、不安定な覚醒状態が長引くことも。
- その結果、「頭は冴えているのに、心は沈んでくる」というギャップが生まれ、気分の揺れや不安感が出やすくなります。
2. “夕暮れ時”特有の心理状態
- 「黄昏反応(たそがれ症候群)」という言葉もあるように、夕方は感情が敏感になりやすい時間帯。
- 特に認知症やうつ状態にある方は、夕暮れになると落ち着かなくなったり、感情が不安定になる傾向があります。
- 夏のセミの声や、夕焼けの色、日中との温度差など、季節的な刺激も感情を揺さぶる要因になります。
訪問看護の現場で見られる変化
- 「夕方になると妙に不安が強くなる」「同じことを何度も聞くようになる」
- 「暗くなる前に部屋の照明をつけ始める」「急に人恋しくなる」「過去の話を繰り返す」
- 「落ち着かず家の外に出たがる」「テレビをつけっぱなしにする」など、普段と違う行動パターンが見られることも
夕暮れの気分変動への具体的な対応策
1. 環境を整える
- 夕方の明るさが変わる前に早めに照明をつけて、部屋の明るさを一定に保つ
- 静かな音楽を流す、カーテンを閉めるなど、安心できる「夕方ルーティン」を整える
- 急な暗さ・静けさが不安を生まないように、ゆるやかに“夜モード”へ移行させる
2. 声かけ・関わりの工夫
- 「今の時間、なんとなく落ち着かないことってありますか?」など、気分に寄り添った声かけ
- 「少しストレッチしましょうか」「お茶をいれますね」など、軽い作業や対話で気分を切り替える
- 不安が強い利用者には、「あと30分で〇〇の時間ですね」など、時間の見通しを示すことで安心感を持たせる
3. 本人の“安心スイッチ”を活用する
- 「お気に入りの飲み物」「決まったテレビ番組」「ペットとのふれあい」など、落ち着ける習慣や物を確認して活用
- 感情が揺れやすい時間帯に無理な説明や変化を求めないことも大切
家族・支援者と共有しておきたいこと
- 「夕方は気分が落ち込みやすい時間です」と事前に共有することで、本人への対応の工夫が生まれやすくなる
- 家族にとっても「なぜ急に不安定になるのか」が分かると、対応への戸惑いが減る
まとめ
夏の夕暮れは、心が静かに揺れる時間です。特に精神的に敏感な方にとっては、「なんとなく不安」「自分でも理由が分からないけど落ち着かない」という時間帯でもあります。
だからこそ、訪問看護ではその“揺れ”に気づき、環境や声かけを通して「大丈夫ですよ」という安心感を届けていくことが大切です。
「夕方が怖くなくなった」「なんとなく安心できるようになった」――そんな変化の一歩を、私たちの関わりから生み出していきましょう。
お盆期間のメンタルケア:帰省や家族関係のストレスに向き合う
〜「みんなが集まる季節」に感じる孤独・プレッシャーへの寄り添い〜
はじめに
8月といえば、「お盆」の季節です。家族や親戚が集まる機会が増え、久しぶりの再会や会話に心が温まる場面も多い一方で、精神的な負担や緊張、孤独を感じる方も少なくありません。
特に精神疾患を抱える方にとっては、お盆の“非日常”が生活リズムの乱れや不安の引き金になることもあります。
この記事では、訪問看護の視点から「お盆時期に起こりやすいメンタルの変化」と「それに対する具体的なケア方法」についてご紹介します。
お盆シーズンに起こりやすい心の変化
1. 「帰省できない/しない」ことへの孤独感
- 実家に戻ることが難しい、家族関係に距離がある、などの事情から“ひとりのお盆”を過ごす利用者も多くいます。
- SNSやテレビで「家族団らん」の映像を見ることで、孤独や疎外感を強く感じてしまうことがあります。
2. 家族との再会によるプレッシャー・緊張
- 「ちゃんとして見られたい」「元気にふるまわなければ」と無理をして疲弊してしまうケースも。
- 家族との会話の中で、病気や生き方についての無意識な“干渉”や“否定”に傷ついてしまうことも。
3. 非日常による生活リズムの乱れ
- 家族が在宅になったり、来客が増えることで普段のペースが乱れやすくなる
- 外食や移動が続くことで、睡眠や服薬のリズムが崩れやすい
訪問看護の現場でできる支援
1. 「いつも通りの関わり」が安心につながる
- 訪問日程を大きくずらさず、「お盆もいつも通りに訪問しますよ」と伝えるだけで安心感を得られるケースもあります。
- “非日常の中にある日常”の提供が精神的な安定を支える大きな鍵になります。
2. 気持ちの揺れに気づき、そっと寄り添う
- 「家族とは会えそうですか?」「お盆はどんな風に過ごす予定ですか?」とさりげない会話で心の状態を把握
- 急に涙を流したり、話題を避ける様子があれば、無理に聞き出さず、安心できる話題に切り替える配慮を
3. 体調・生活リズムの確認と調整
- 普段より寝不足・疲労・胃腸の不調などが出やすい時期です
- 睡眠・食事・服薬の乱れが見られる場合は、記録やタイマー利用などのサポートを提案することも有効
ご家族への支援・声かけのポイント
- 「お会いできるのを楽しみにしていた」「元気そうで安心した」といった肯定的な言葉で始めることが大切
- ご本人の前で病状・服薬・通院についての議論が加熱しすぎないよう配慮を
- ご家族が不安や負担を抱えている場合は、相談窓口や支援制度の情報提供を行いましょう
まとめ
お盆の時期は、見えにくい「心の揺れ」が多く起こりやすいタイミングです。
大切なのは、「特別なことをしようとする」よりも、普段通りの関わりを丁寧に行うこと。
訪問看護だからこそできる“寄り添い”で、利用者の方が「安心してこの時期を乗り切れた」と思えるようなサポートを届けていきましょう。
夏季の訪問看護:服装と衛生管理の工夫
〜暑さにも感染症にも負けない、快適で安全な訪問を目指して〜
はじめに
夏は、訪問看護師にとっても体力を消耗する季節です。強い日差し、高温多湿な気候、室内外の温度差など、体への負担は想像以上です。
さらに、新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルスなど感染症のリスクが夏でも残っていることから、衛生管理の徹底も求められます。
本記事では、夏の訪問看護を安全かつ快適に行うための「服装選びの工夫」と「衛生管理のポイント」についてご紹介します。
夏季の服装:快適さと清潔感の両立がポイント
1. 通気性・吸湿性の高い素材を選ぶ
- ポリエステル+綿などの速乾性のある素材がおすすめ
- 汗をかいてもべたつかず、清潔感を保てる
- 襟付き・ポケット付きのシャツは機能性と信頼感を両立
2. 色は明るめで涼しげに
- 黒や紺などの濃色は熱を吸収しやすいため、白・ベージュ・水色などを選ぶと◎
- 見た目にも爽やかで、利用者に与える印象も良好
3. UV対策を忘れずに
- 帽子やアームカバー、UVカットの上着などで紫外線対策
- 移動中の体力消耗を防ぎ、日焼けによる体調不良も予防
4. 着替えの準備を
- 替えのシャツやインナーを車内やバッグに常備
- 訪問の合間にサッと着替えるだけで、快適さと衛生感を保てる
衛生管理のポイント:夏でも油断禁物!
1. マスク・手指消毒の基本の徹底
- 夏でもマスクは感染対策の基本(ただし屋外や移動中は熱中症に注意)
- 訪問ごとの手洗い・手指消毒は必須
- 汗をかいて湿ったマスクは、早めに交換
2. 汗対策は感染予防にもつながる
- 汗で湿った服やタオルは、雑菌の温床に
- 吸湿速乾タオルや冷感インナーを活用して快適さと清潔を両立
3. 携帯用衛生グッズを常備
- ポータブルファンや冷却シートで熱対策
- アルコールスプレー、除菌シート、制汗剤などを移動カバンに常備
4. 訪問先での清潔対応
- 訪問先で汗を拭くときは、使い捨てタオルまたは個包装の清拭シートを使用
- 衣服の臭い・汗染みは利用者への配慮としても重要
現場での工夫例
- 汗ばむ前に制汗スプレーで事前ブロック
- 車移動の際はエアコン使用+日除け設置
- 訪問先の室温チェックと水分摂取の声かけもルーチンに
- 「今日も暑いですね」といった会話で心理的距離を縮める工夫も大切
まとめ
夏の訪問看護は、ただでさえ体力と神経を使う仕事に、暑さと衛生への対応という二重の負担がかかります。
しかし、服装やグッズを工夫し、衛生対策を習慣化することで、体調不良も感染リスクも大きく減らすことが可能です。
スタッフが快適であることは、そのまま利用者への安心感や信頼にもつながります。
「無理なく」「心地よく」働ける夏の訪問スタイルを、ぜひ実践していきましょう。
花火大会や祭りの音:感覚過敏への配慮
〜夏のイベントを安心して過ごすためにできること〜
はじめに
夏といえば、花火大会や夏祭り、盆踊りといった賑やかなイベントが各地で開催されます。楽しい思い出となるこれらの行事ですが、感覚過敏を持つ方にとっては、強いストレスや不安の原因になることも少なくありません。
特に精神疾患や発達障害、認知症のある方は、大きな音・人混み・光の刺激に対して過敏に反応する傾向があります。この記事では、訪問看護の現場で役立つ、感覚過敏の方への具体的な配慮と対応方法をご紹介します。
感覚過敏とは?
1. 音や光に対して「異常に敏感」
感覚過敏とは、視覚・聴覚・触覚などの感覚に対して、通常よりも強く不快感や苦痛を感じる状態です。とくに夏の花火や祭りでは次のような刺激が問題となります:
- 大きな爆発音・打楽器・拡声器の声
- 点滅する光、強い照明
- 人混みや熱気、汗のにおい など
2. 精神疾患と感覚過敏の関係
- 統合失調症やうつ病、不安障害では、外部刺激に過敏になることがあります。
- ASD(自閉スペクトラム症)やADHDを併発している方は、過剰な音や光でパニックやパーソナルスペースの崩壊が起きやすくなります。
夏のイベント時に起こりやすいトラブル
- 花火の音に驚いて外に飛び出してしまう
- 騒音に耐えられず、激しい怒り・パニック・混乱を起こす
- 予期せぬ音(屋台の呼び声、太鼓、群衆の声)で気分が不安定に
- 過刺激により、その後数日間の体調不良や不眠に繋がる
訪問看護でできる事前の備え
1. イベント予定の把握と周知
- 花火大会や祭りの日程を事前に調べ、利用者本人・家族・支援者と情報共有
- 「〇月〇日〇時頃に近くで大きな音がします」といった予測と心構えを伝えるだけでも安心感につながります
2. 環境調整・刺激の遮断
- イヤーマフ、ノイズキャンセリングイヤホン、遮音材の活用を提案
- 遮光カーテンやサングラスで視覚刺激を軽減
- 外出を控え、静かな時間・空間を確保する計画を立てる
3. 代替行動や安心アイテムを用意
- 音楽・読書・好きな香りなど、安心できるルーティンや刺激を準備
- 不安時に手に取れる「お守り」「ぬいぐるみ」「触感グッズ」なども有効
4. 家族・支援者への声かけ
- 「〇〇さんは音に敏感です。花火の時間帯は声かけを増やしましょう」など、見守りと理解の協力を依頼
- パニック時の対応マニュアル(声をかける言葉・避難場所など)を共有
もし当日パニックが起きたら
- 無理に止めたり叱ったりせず、安心できる空間へ誘導
- 「今はうるさいけど、〇分で終わるよ」など、時間の見通しを示す
- 水分補給・深呼吸など、落ち着ける声かけを心がける
- 必要であれば、主治医や家族に状況を報告し、対応を相談
まとめ
感覚過敏の方にとって、花火大会や夏祭りは「楽しいイベント」ではなく、「乗り越えるべき負荷」になることもあります。
しかし、事前の準備や配慮、周囲の理解があれば、不安を最小限に抑え、安全に過ごすことが可能です。訪問看護の中でできるちょっとした一言や工夫が、ご本人の安心につながります。
この夏、すべての人が自分らしく過ごせるよう、私たちの役割が大切です。
夏の睡眠障害:日照時間と体内リズムの関係
〜眠れない、起きられない…夏特有のリズムの乱れにどう対処するか〜
はじめに
夏になると、「なかなか寝つけない」「朝早く目が覚めてしまう」「昼間に眠くてぼーっとする」といった睡眠のトラブルを感じる方が増えてきます。特に、精神疾患をお持ちの方は、季節による体内リズムの変化に敏感であり、睡眠障害が気分の不安定さや体調悪化につながることもあります。
この記事では、夏の「日照時間」が私たちの体内時計(概日リズム)にどのような影響を与えるのか、また、精神的な不調を悪化させないための睡眠対策について、訪問看護の視点も交えながらご紹介します。
夏の睡眠障害と「日照時間」の関係
1. 日照時間が長くなることで起こるリズムの乱れ
夏は日の出が早く、日没が遅くなるため、自然光を浴びる時間が長くなります。これは一見良いことのように思えますが、次のような影響を及ぼします。
- 朝早く光を浴びることで睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌が早まる
- 夕方になっても明るいため、脳が「まだ昼間」と錯覚して眠くなりにくくなる
- 結果として、「早朝覚醒」「寝つきの悪さ」などの睡眠障害が生じやすくなる
2. 精神疾患との関連性
- うつ病や双極性障害の方は、体内時計の乱れによって、気分の変動が激しくなることがあります。
- 統合失調症の方では、睡眠の乱れが幻覚・妄想の悪化を招く可能性も。
- 睡眠がうまくとれないことで、昼夜逆転や生活リズムの崩壊が起こりやすくなります。
睡眠を整えるための具体的な対処法
1. 朝の光を“コントロール”する
- カーテンを遮光性の高いものにする
- 早朝に日差しが差し込まないよう、寝室の向きを工夫する
- 起床時間の1時間前から光が入る仕組み(タイマーライトなど)を利用するのも効果的
2. 夜の「入眠スイッチ」を作る
- 寝る1時間前からはスマホやTVの画面を控える(ブルーライト対策)
- お風呂・音楽・ストレッチなど、「夜の習慣」を取り入れることで副交感神経を優位にする
- エアコンや扇風機で室温を快適な睡眠環境を整える
3. 日中の活動とリズムを意識する
- 朝食をしっかり摂ることで体内時計を“朝モード”にリセット
- 午前中に軽い運動や日光浴(10〜15分)を行うと、睡眠の質向上につながる
- 昼寝は15〜20分以内にとどめることで、夜の睡眠への影響を抑える
訪問看護でのサポートのポイント
- 利用者の睡眠時間・質・日中の様子などを観察し、リズムの乱れを早期に発見
- 簡単な睡眠記録表や「起床時間だけは固定しましょう」などの目標設定も有効
- 医師に相談の上、必要に応じて睡眠薬やメラトニン作動薬の調整を支援
- 「眠れない=不安・焦り」になりがちな利用者には、「焦らなくて大丈夫」と声をかけることが大切
まとめ
夏の長い日照時間は、気づかぬうちに心身のリズムに影響を与え、睡眠の質やメンタルバランスの乱れを引き起こします。
訪問看護の現場では、睡眠状態の把握と日中活動の提案、環境調整の支援が重要な役割となります。
睡眠が安定すれば、心も体も自然と整っていきます。
ぜひ、この夏のケアに役立ててください。
夏バテとメンタルヘルス:食欲不振への対応
〜「食べられない」が心にも影響する理由とその工夫〜
はじめに
暑さが続く夏は、身体だけでなく心にも影響を与える季節です。特に、食欲不振(食べられない、食が進まない)は「夏バテ」の代表的な症状ですが、精神的な不調を招く一因にもなり得ます。
精神疾患をお持ちの方にとっては、栄養の偏りが気分の波や疲労感を悪化させるリスクもあるため、早めの対応が大切です。
今回は、夏の暑さによる食欲不振とメンタルヘルスの関係、そして実践的な栄養補給の工夫についてご紹介します。
食欲不振とメンタルヘルスの関係
1. 栄養不足が「心のガソリン切れ」に
脳の働きにはブドウ糖、ビタミン、鉄分、タンパク質などの栄養素が欠かせません。食事が不規則になると、集中力の低下・不安感の増加・抑うつ気分など、精神症状の悪化につながる可能性があります。
2. 体力低下は意欲の低下にも
暑さで汗をかきすぎたり、十分に食べられなかったりすると、倦怠感や動きたくない感覚が強くなります。それが長引くと「何もしたくない」「横になっていたい」という気分の落ち込みを助長することもあります。
3. 「食べたくない」が孤立感につながることも
食事を拒否する状態が続くと、家族や支援者とのコミュニケーションが減る場合があります。特に独居の方では、「一人で食べるのが寂しい」「誰にも気づかれずに体調が悪化した」ということも。
訪問看護の現場でよくある声
- 「暑くて何も食べたくない。冷たい水だけ飲んでいる」
- 「そうめんばかりになって、栄養が偏っている気がする」
- 「食事の支度が面倒になってきて、1日1食しか食べていない」
こうした声は、夏の訪問看護の現場ではよく聞かれます。そのため、無理せず続けられる工夫を一緒に見つけていくことが大切です。
食欲がないときの栄養補給の工夫
1. 少量・高栄養の工夫をする
- ゼリー飲料や栄養補助食品(エネルギーゼリー、バランス栄養食など)
→ 食事が進まないときの代替に。冷やすとさらに食べやすくなります。 - たんぱく質を含む飲み物(豆乳、ヨーグルトドリンク、プロテイン)
→ 飲み物として取り入れられるので、食事が苦手でも摂りやすい。
2. 見た目と温度で「食べたい」を引き出す
- 色とりどりの野菜やフルーツを取り入れる(トマト、キュウリ、スイカなど)
- 冷たい料理(冷製スープ、冷やし茶漬け、冷やしうどんなど)を活用する
3. 食事の「回数」にこだわらない
- 1日3食にこだわらず、1日5~6回の小分けスタイルでもOK
→ 負担を減らし、少しずつエネルギーを取り入れる工夫が重要です。
4. 「一緒に食べる」ことの力を活かす
- 訪問看護の時間帯に合わせて「一口だけ食べてみませんか?」と提案する
- 家族や支援者と一緒に食卓を囲むことで、食事の意欲が高まるケースもあります
訪問看護でできるサポート
- 食事内容や摂取状況の確認と、必要に応じた栄養士や主治医との連携
- 食べられそうなメニューの提案(レシピカードや画像の活用も効果的)
- 体重の変化、脱水や栄養失調の兆候(皮膚の乾燥・浮腫・口腔の状態など)の観察
- 「無理に食べさせる」ではなく、「一口でも食べてみよう」という寄り添いの姿勢
まとめ
夏の食欲不振は、ただの「夏バテ」ではなく、メンタルの不調の引き金にもなります。
無理に食べさせることなく、「少しでも体が楽になる食べ方」「続けられる食習慣」を一緒に見つけていくことが、精神科訪問看護においてとても大切です。
心と体をつなぐ“食”のケアで、この夏を少しでも健やかに過ごしていただけますように。
【お知らせ】若年がん患者等の在宅療養支援助成事業について
~土浦市にお住まいの40歳未満のがん患者さま・ご家族へ~
皆さま、こんにちは。
本日は、土浦市より実施されている「若年がん患者等在宅療養支援助成事業」について、当ステーションより情報提供いたします。
この制度は、40歳未満で在宅療養をされるがん等の患者さまが、住み慣れたご自宅で安心して過ごせるよう、訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具の利用費の一部を助成するという内容です。
対象となる方
以下すべてに該当する方が対象です。
- 土浦市に居住し、住民登録のある方
- サービス利用時点で40歳未満の方
- 末期がん等で、医師から介護保険の要介護状態と同等と診断された方
助成対象となるサービス
1. 訪問介護
入浴・排せつ・食事などの介助や、家事援助(掃除・洗濯など)
2. 訪問入浴介護
専用の浴槽を持ち込んで行う入浴サービス(看護職員1名+介護職員2名で対応)
3. 福祉用具のレンタル
車いす・電動ベッド・歩行器・手すりなど、必要な用具の貸与
4. 福祉用具の購入
入浴補助用具・腰掛便座・簡易浴槽など
※「いばらきがん患者トータルサポート事業(県)」との併用は可能です。
助成内容(例)
- 利用料に対して9割を助成(生活保護受給者は10割)
- 上限:月63,000円(生活保護受給者は70,000円)
<例> 訪問入浴介護(週2回、月8回利用)の場合
1回12,500円 × 8回 = 100,000円
→ 100,000円 × 0.9 = 90,000円 → しかし上限が63,000円 → 助成額は63,000円
利用までの流れ
- 交付申請
→ 医師意見書を添えて土浦市健康増進課へ提出 - サービス利用・自己負担で支払い
→ 利用分の領収書や明細を保管 - 実績報告・請求
→ 毎月報告し、市が審査・助成額を通知 - 助成金の振込
→ 指定口座へ助成金が振り込まれます
ご相談・お問い合わせ先
土浦市 健康増進課(健康支援係)までお気軽にご相談ください。
📞 電話番号:029-826-3471
📄 詳細はこちら
👉 土浦市公式サイト:若年がん患者等在宅療養支援助成事業ページ
おわりに
介護保険の対象とならない40歳未満の方が、自宅で安心して療養生活を送るために
この制度が、少しでも負担軽減と安心につながることを願っております。
熱中症と精神疾患:服薬と体温調節の注意点
〜抗精神病薬・抗うつ薬を服用中の方とそのご家族へ〜
はじめに
夏になると毎年ニュースでも話題になる「熱中症」。実は、精神疾患を持つ方々にとっては、特に注意が必要な季節です。
その理由の一つが、「服薬」と「体温調節機能」の関係にあります。精神科治療で処方される薬の中には、体温を上昇させたり、暑さに気づきにくくさせたりする作用があるものがあるのです。
この記事では、精神疾患をお持ちの方やそのご家族、そして訪問看護に関わるスタッフの方に向けて、熱中症リスクとその予防についてわかりやすく解説します。
なぜ精神疾患のある方は熱中症にかかりやすいのか?
1. 体温調節機能の低下
抗精神病薬(例:オランザピン、クロルプロマジンなど)や抗うつ薬の一部には、発汗機能を抑制する作用があるため、汗をかきにくくなり体温が上がりやすくなります。
また、薬の影響で「暑い」と感じにくくなることもあり、自覚症状のないまま熱中症が進行することもあります。
2. 薬による脱水
抗コリン作用を持つ薬は口渇(のどの渇き)や排尿の抑制を引き起こすことがあります。水分を十分に取らないことで脱水状態となり、熱中症のリスクが高まります。
3. 環境への対応が難しいケース
統合失調症やうつ病、認知症などをお持ちの方は、エアコンの使用を控える、外出を控えない、厚着をしてしまうなど、季節に合わない行動を取ってしまうこともあります。
熱中症予防のためにできること
1. 環境の工夫
- 室温を28℃以下に保つ(エアコンや扇風機を活用)
- カーテンやすだれで直射日光を避ける
- 夜間や早朝の涼しい時間帯に外出するよう促す
2. 服装と持ち物
- 通気性・吸湿性の良い薄手の衣類を着る
- 帽子や日傘、冷却グッズ(首元冷却タオル等)を使用する
3. 水分・塩分補給
- こまめな水分補給を忘れずに(1日1.5〜2Lを目安)
- 汗をたくさんかいた時は、塩分も適度に摂取する(スポーツドリンクや経口補水液など)
4. 観察と声かけ
- 顔が赤い、異常な発汗や逆に汗が出ていない、ふらつきや倦怠感があるなど、いつもと違う様子があれば注意
- 「暑くない?」「水分ちゃんと摂ってる?」とさりげない声かけを継続する
訪問看護師ができるサポート
- 薬の副作用と熱中症の関係を説明し、ご本人やご家族と情報共有する
- 室温の確認や水分補給の声かけを、訪問時に積極的に行う
- 症状の変化や脱水のサインを観察し、必要時には主治医に相談する
おわりに
熱中症は、予防ができる病気です。しかし、精神科の薬を服用されている方はリスクが高く、自分で気づきにくいという特性もあります。
だからこそ、訪問看護やご家族のサポートがとても重要です。この夏、心と体の両面を守るために、ぜひ今日からできる対策を取り入れてみてください。
熱中症とは?原因とメカニズムを分かりやすく解説
夏が近づくと、「熱中症」という言葉をよく耳にします。しかし、実際にどのような仕組みで起こるのか、正しく理解している人は少ないかもしれません。今回は、熱中症の原因やメカニズムをわかりやすく解説し、予防のために知っておくべきポイントを紹介します!
1. 熱中症とは?
熱中症とは、体温の調整がうまくできなくなり、体に熱がこもってしまうことで起こる健康障害です。重症化すると、意識障害や臓器不全を引き起こし、最悪の場合、命に関わることもあります。
2. 熱中症が起こるメカニズム
(1)体温調節の仕組み
私たちの体は、暑いときに「汗をかく」ことで体温を下げています。汗が蒸発すると、皮膚の熱が奪われ、体が冷やされるのです。しかし、高温多湿の環境では汗が蒸発しにくく、体に熱がこもりやすくなります。
(2)熱中症が発生する流れ
1. 気温や湿度が高くなる → 体温が上昇しやすくなる
2. 汗をかいて体温を下げようとする
3. 大量の汗で水分・塩分が失われる
4. 体の水分バランスが崩れ、血流が悪化
5. 体温調節ができなくなり、熱が体内にこもる
6. 熱中症の症状が現れる(めまい・頭痛・倦怠感など)
特に、湿度が高いと汗が蒸発しにくく、体温が下がりにくくなるため、熱中症のリスクが高まります。
3. 熱中症の主な原因
熱中症は、以下のような環境や体の状態が影響して起こります。
🌞 環境要因
■ 気温が高い(30℃以上でリスク増加)
■ 湿度が高い(60%以上で汗が蒸発しにくい)
■ 風がない(汗が乾かず体温が下がらない)
■ 閉め切った室内(熱がこもりやすい)
■ 強い日差し(直射日光で体温が上昇)
💧 体の状態
■ 水分・塩分不足(発汗で体内のミネラルが失われる)
■ 寝不足・疲労(自律神経の働きが乱れ、体温調節が鈍る)
■ 高齢者・乳幼児(体温調節機能が弱い)
■ 肥満・持病がある(体に熱がこもりやすい)
■ 暑さに慣れていない(急な気温上昇で適応できない)
4. 熱中症の症状と重症度
熱中症の症状は軽度から重度まであり、早めの対応が重要です。
🔹 軽度(I度)
■ めまい・立ちくらみ
■ 筋肉のこむら返り(足がつる)
■ 大量の発汗
→ 対処法:水分・塩分補給、涼しい場所で休む
🔸 中度(II度)
■ 頭痛・吐き気・嘔吐
■ 強い倦怠感・脱力感
■ 体温が高いのに汗が出ない
→ 対処法:水分補給+体を冷やす(首・脇・足の付け根)
🔺 重度(III度)
■ 意識がもうろうとする・呼びかけに反応しない
■ けいれん・意識障害
■ 体温が40℃以上に上昇
→ 対処法:すぐに救急車を呼ぶ!冷却処置を行いながら搬送
5. まとめ
🔹 熱中症を防ぐために
■ こまめな水分・塩分補給をする(喉が渇く前に!)
■ 涼しい服装・帽子・日傘で直射日光を避ける
■ エアコンや扇風機を活用し、室温を調整する
■ 暑さに慣れるために、無理のない範囲で体を動かす
■ 体調がすぐれないときは無理をせず、休息をとる
熱中症は、正しい知識と予防策を知っていれば防ぐことができます!
暑い季節も元気に乗り切るために、日頃から意識して対策をしていきましょう!
![精神科看護特化型 訪問看護ステーション haru style [ハル スタイル]|茨城県土浦市、かすみがうら市、つくば市、牛久市、阿見町、石岡市、竜ケ崎市](https://haru-style.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-haru_logo.png)