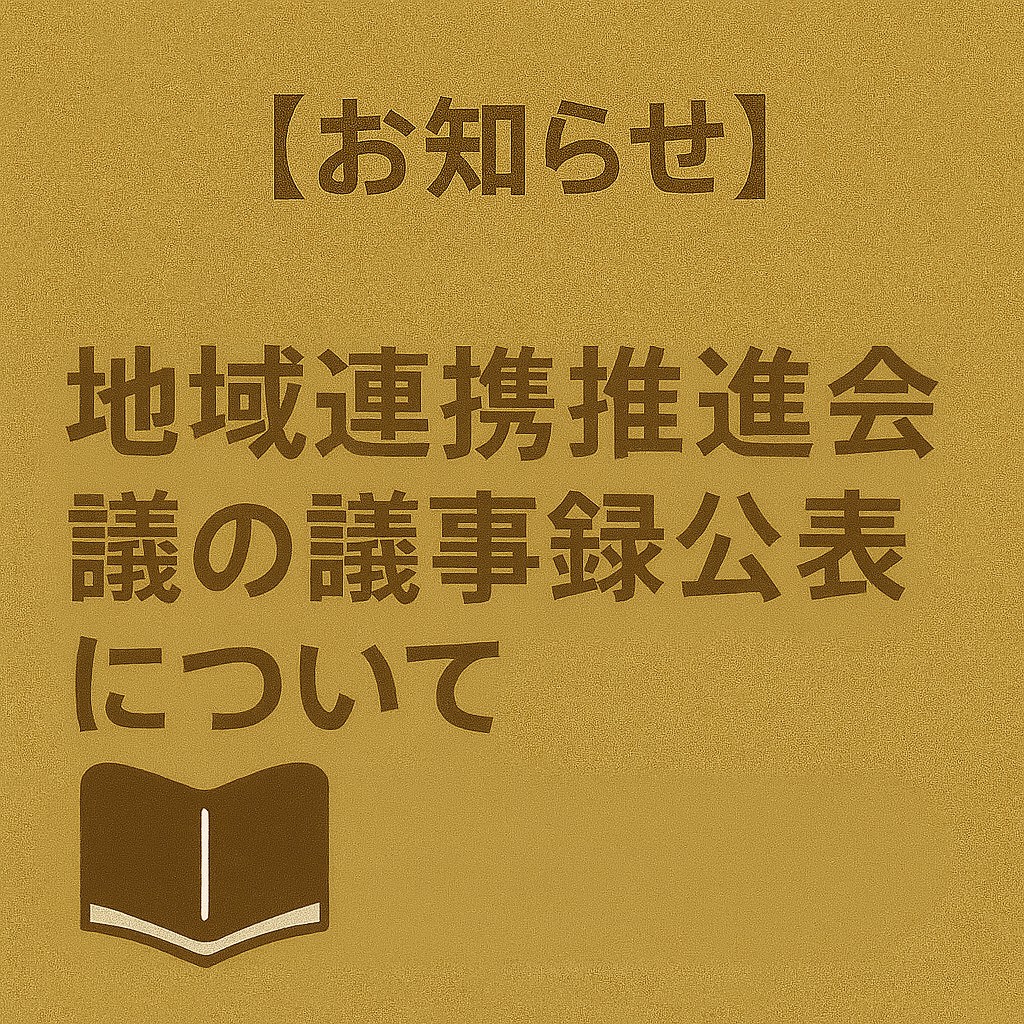〜家庭内でのストレスと支援のポイント〜
はじめに
子どもたちにとっては楽しみな「夏休み」。しかし、精神疾患を抱える方やそのご家族にとっては、生活リズムの乱れや家庭内のストレスを引き起こす要因になることがあります。
訪問看護の現場でも、
- 「子どもがずっと家にいて生活音が気になる」
- 「生活リズムが崩れて、昼夜逆転してしまった」
- 「家族との距離が近すぎて疲れてしまう」
といった声が聞かれます。
この記事では、“夏休み”という非日常がもたらす心と生活への影響を理解し、訪問看護の中でできるサポートのポイントをお伝えします。
夏休みがもたらす生活の変化
1. 家族の在宅時間の増加
- 子どもやパートナーの在宅時間が長くなり、普段の静けさがなくなる
- 食事・洗濯・掃除など家事負担の増加により、ストレスや疲労感が蓄積
2. 生活リズムの乱れ
- 子どもに合わせて起床時間が遅くなり、ご本人の生活リズムまで崩れてしまう
- 「家族が寝てからでないと自分の時間が取れない」と、夜更かし・昼夜逆転になるケースも
3. 心の距離が近すぎて起こる摩擦
- 普段以上に顔を合わせる時間が長くなることで、小さなことで口論になりやすくなる
- ご本人が家族の声や行動に対して過敏になることも
生活リズムの崩れが精神状態に与える影響
- 睡眠時間や食事時間が不規則になることで、気分の波や意欲の低下が強くなる
- 服薬のタイミングがずれ、薬の効果が安定しなくなる
- 「何もできていない」という自己否定感が増し、抑うつ状態やイライラ感が悪化する可能性も
訪問看護での支援のポイント
1. 「非日常」の中で、少しでも「日常」を保つ工夫
- 毎朝の起床・服薬・食事などのタイミングを可能な範囲で固定化する
- スケジュール表やタイマーなどを使い、「次に何をするか」を視覚化するのも効果的
2. 家族との“ちょうどよい距離”を提案
- 「1人で過ごす時間も大切」と伝え、無理に合わせすぎないよう助言
- 家族にも「疲れてしまうのは悪いことではありません」と安心感を持ってもらう声かけを
3. 過剰な刺激・活動量の調整
- 外出やお出かけ、学習など、「やらなければ」というプレッシャーを和らげるサポート
- 誰かと一緒にいる時間が長すぎると疲弊することも。静かな時間の確保を優先
ご家族へのアドバイス・支援
- 夏休みは「うまくいかなくて当たり前」と期待値を下げることで、気持ちが楽になります
- 「何をしてほしいか」「してほしくないか」をご本人と一緒に話し合う場をつくる
- 「少しのストレスは避けられない」と共有し、感情の逃がし方やサポート先(訪問看護など)を明確に
まとめ
“夏休み”という季節の変化は、家庭内の環境や精神状態に見えない影響を与える時期です。
訪問看護では、「非日常の中に日常を取り戻す」ための工夫と、「家族とのちょうどよい関係性の維持」を支えることが大きな役割です。
ご本人もご家族も「この時期を無理なく乗り越える」ことを目指して、必要な支援をさりげなく届けていきましょう。
![精神科看護特化型 訪問看護ステーション haru style [ハル スタイル]|茨城県土浦市、かすみがうら市、つくば市、牛久市、阿見町、石岡市、竜ケ崎市](https://haru-style.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-haru_logo.png)