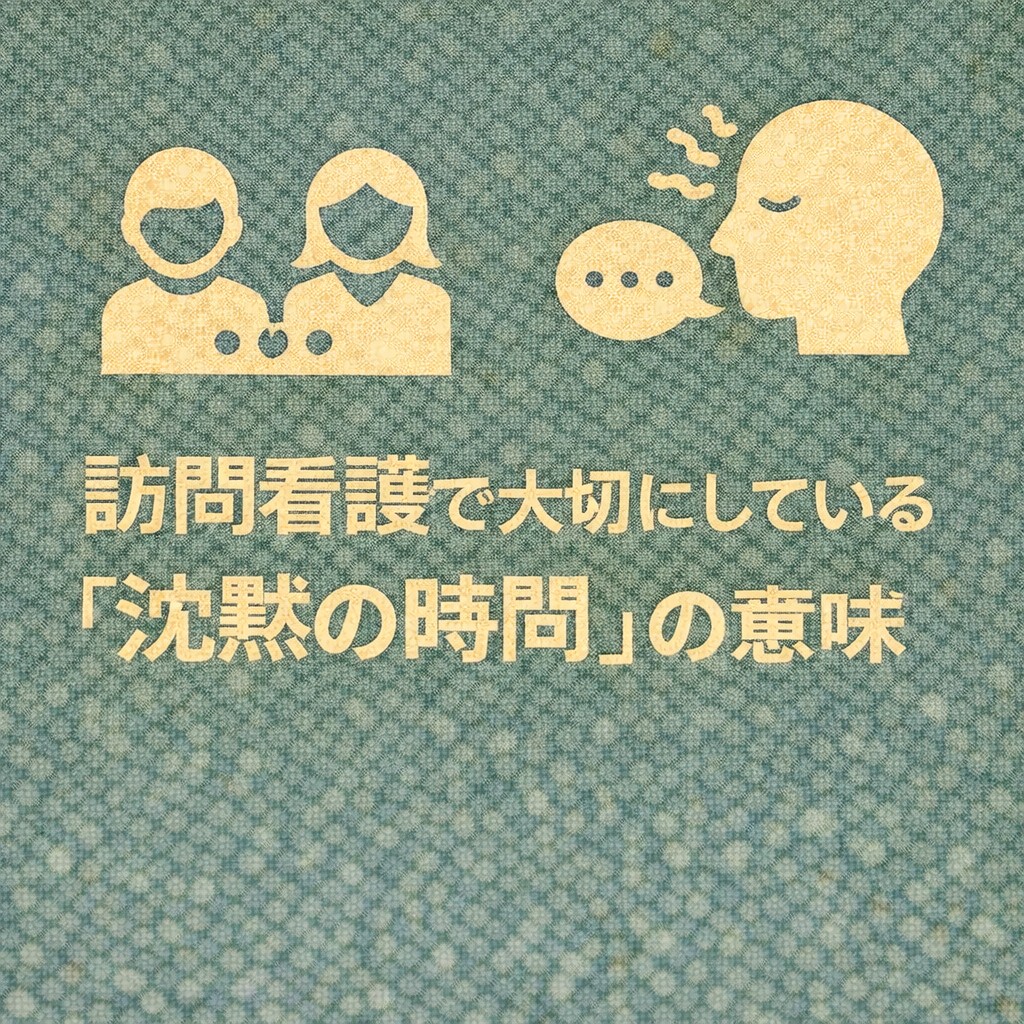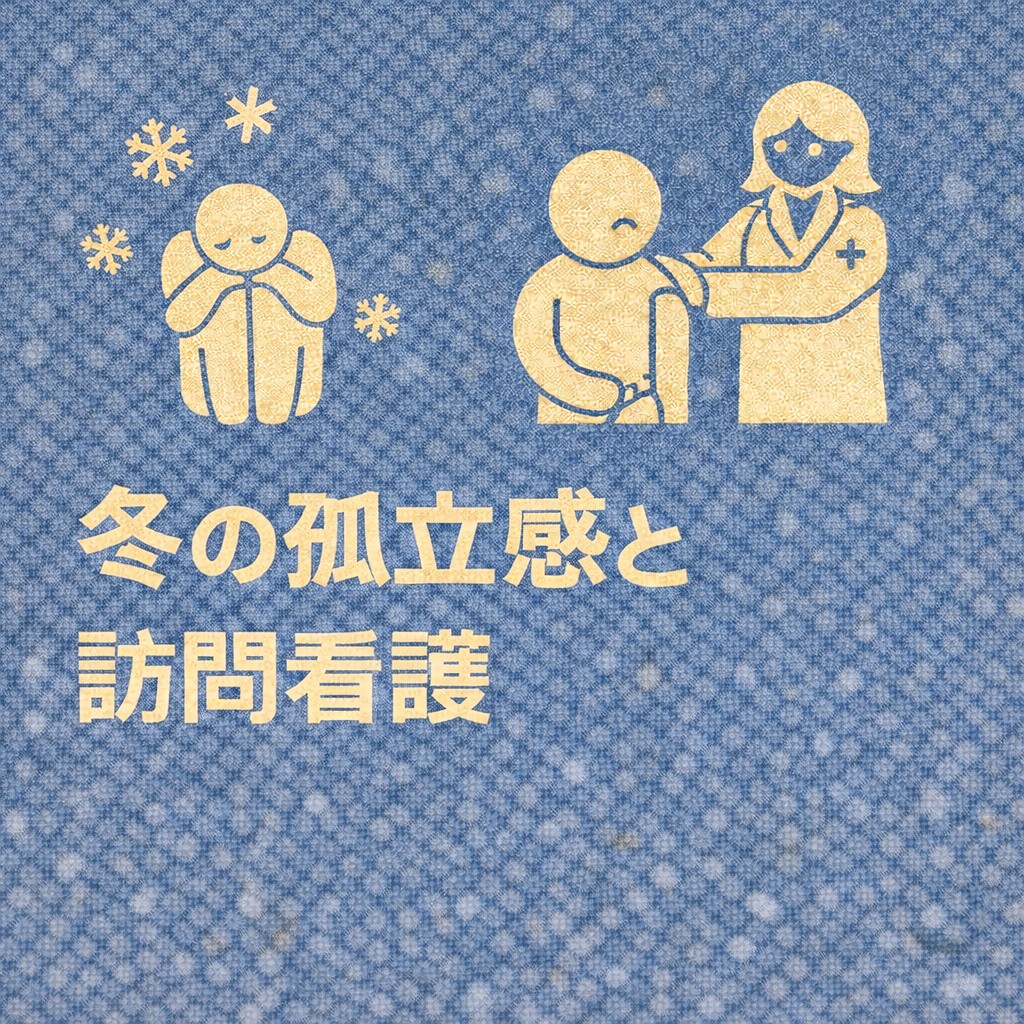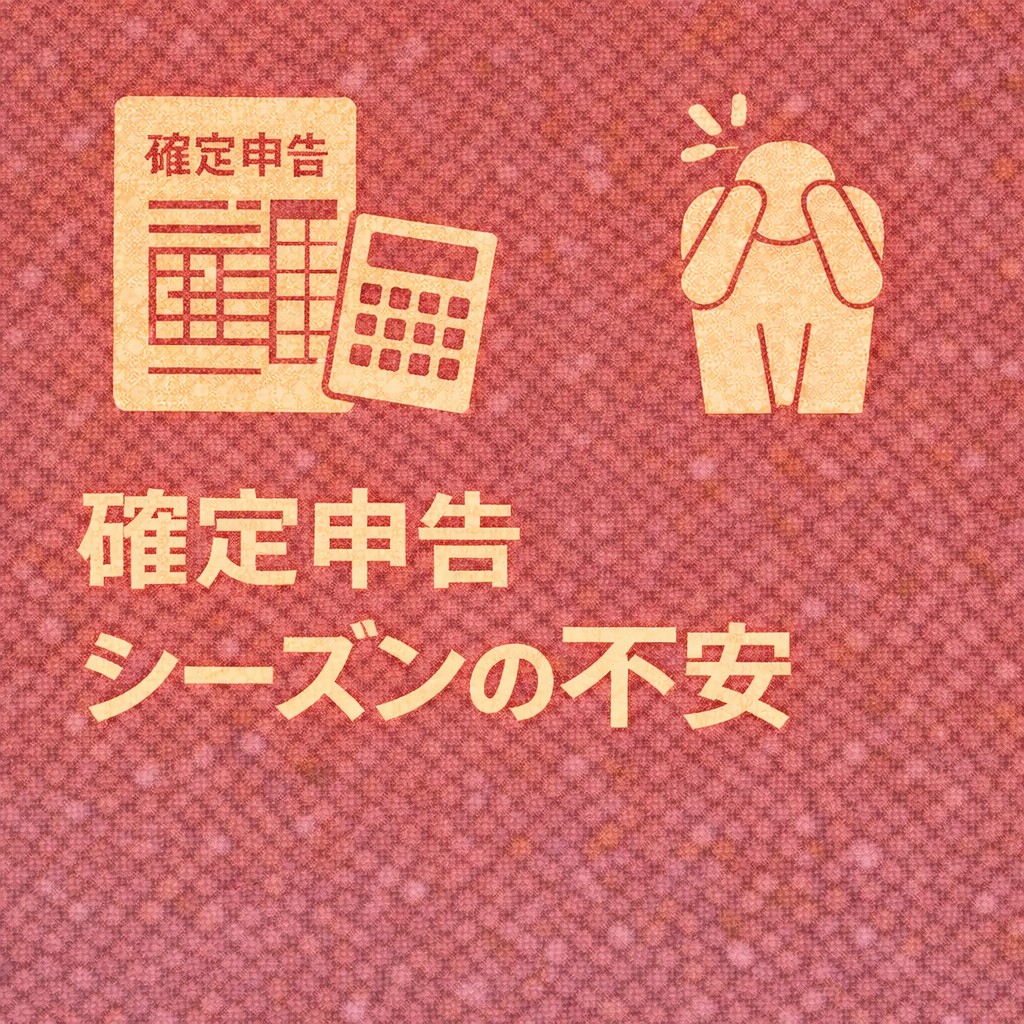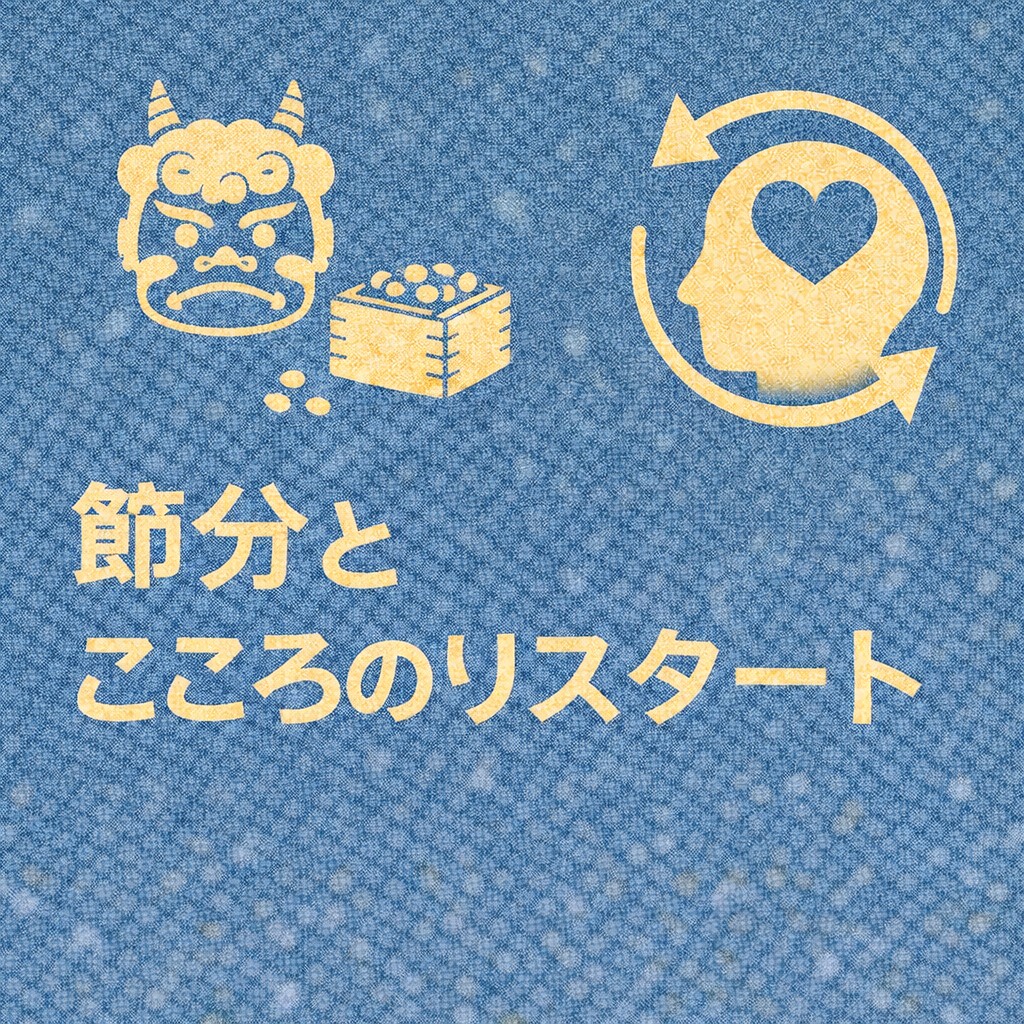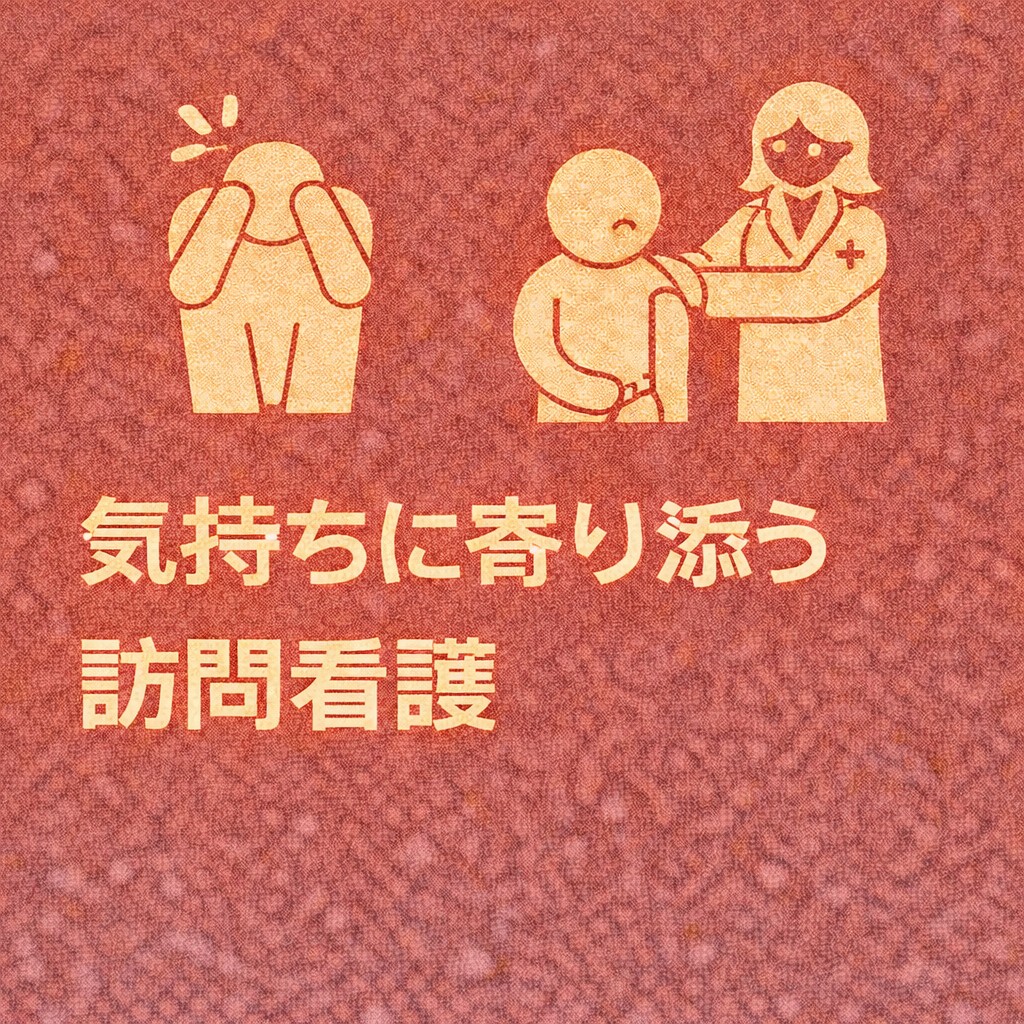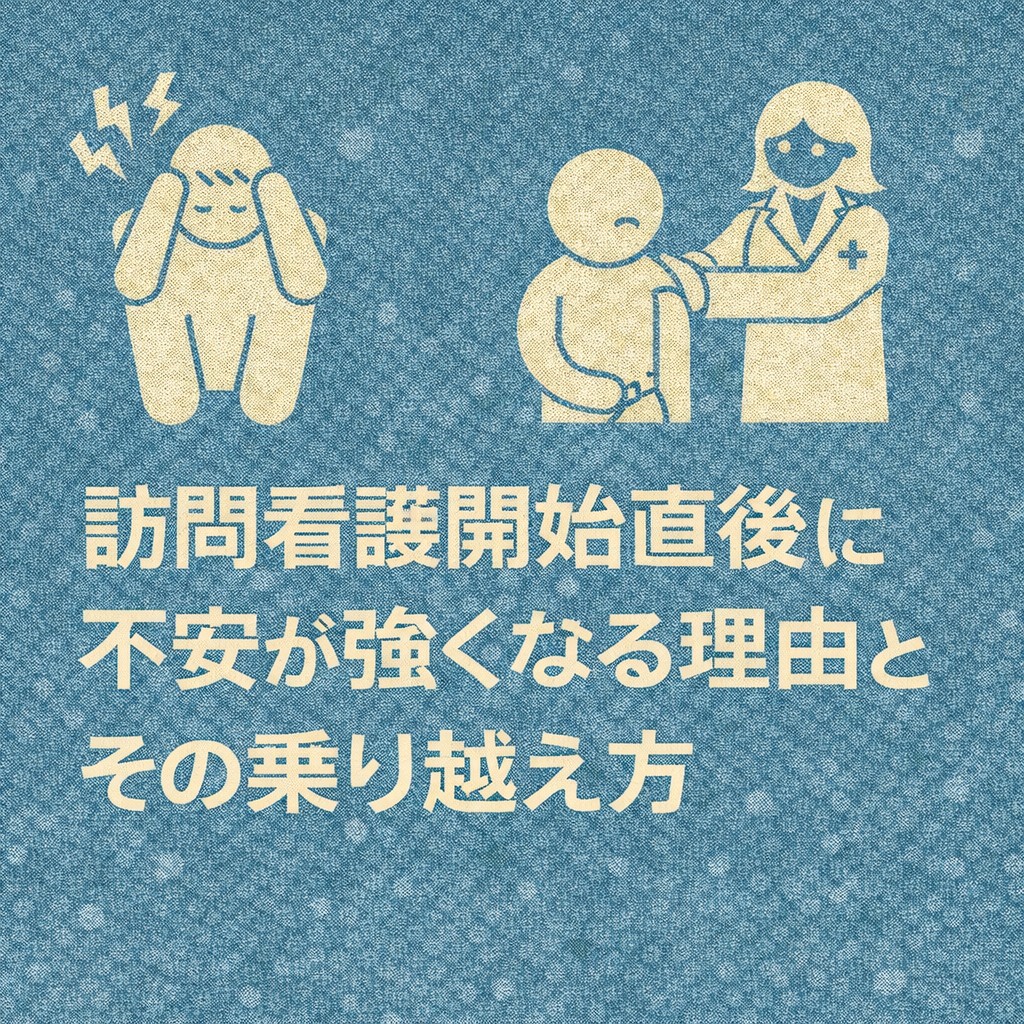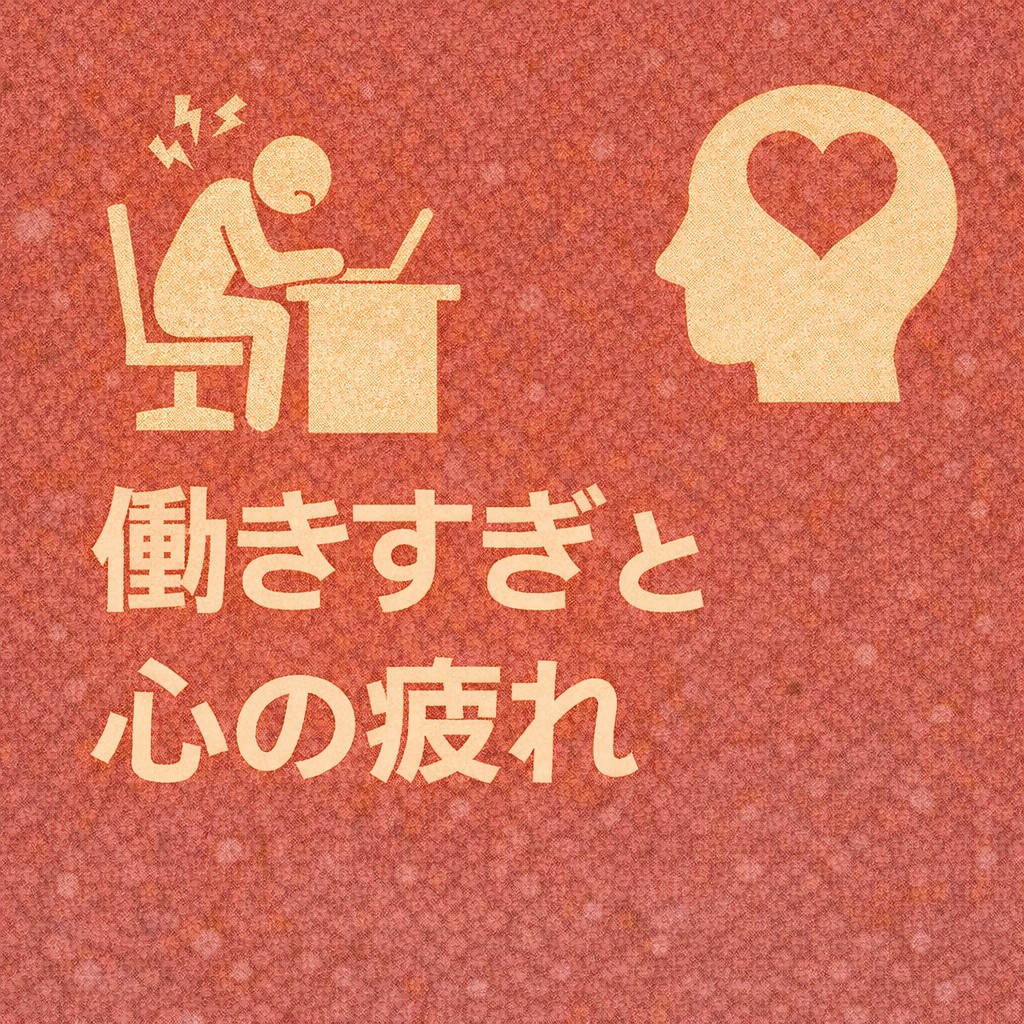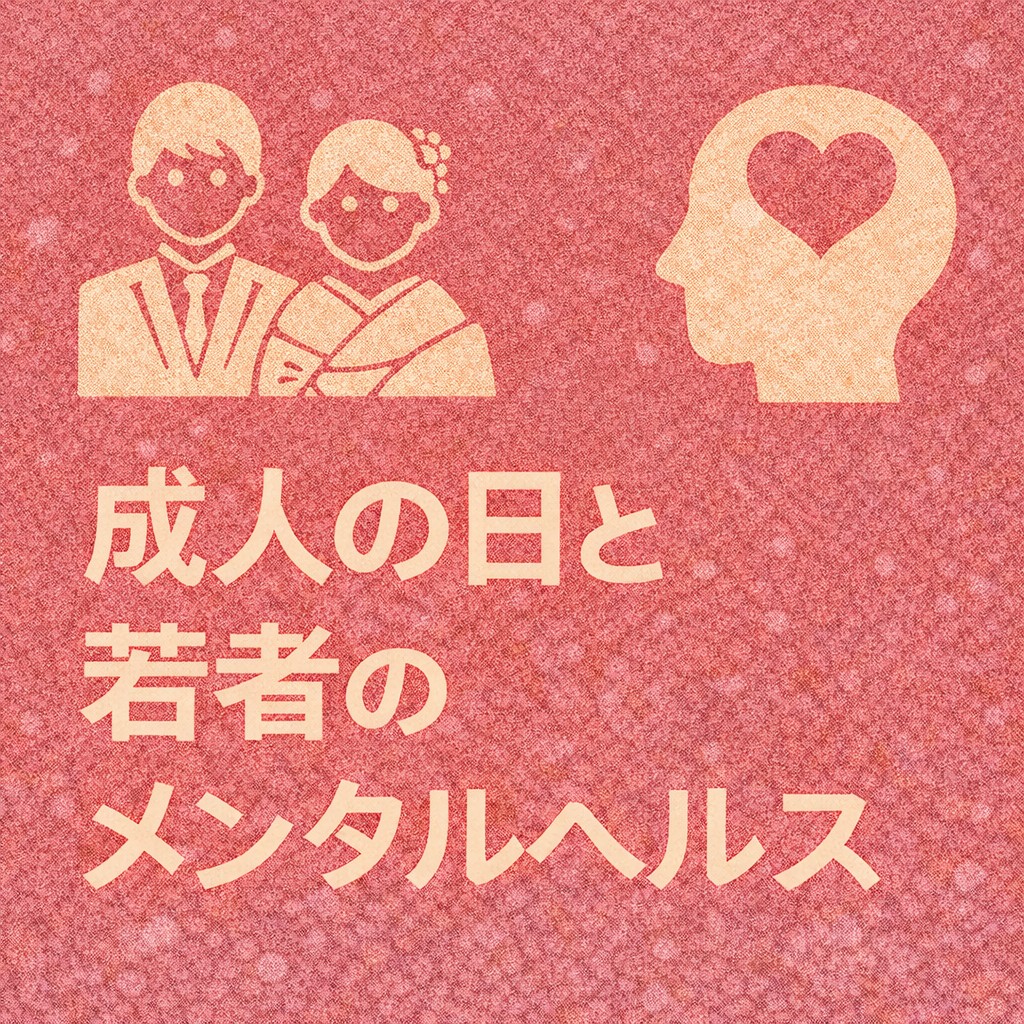〜話さなくても、伝わることがある〜
はじめに
訪問看護では、会話だけでなく、「沈黙の時間」も大切なコミュニケーションのひとつです。
私たちは普段、「話すこと=関わること」と考えがちですが、
精神的な不調や不安を抱える方にとっては、「黙ってそばにいるだけ」の時間が何より安心につながることがあります。
今回は、haru styleが訪問看護の中で大切にしている“沈黙の時間”の意味についてお伝えします。
なぜ、沈黙の時間が大切なのか?
1. 心を休ませる「安全な空白」
訪問の時間は、利用者さまにとって貴重な人との関わりのひとときですが、
それが「ずっと会話を続ける場」である必要はありません。
特に心が疲れているとき、人と話すこと自体がエネルギーを消耗させる場合もあります。
そんなとき、“話さなくてもいい時間”があること自体が、こころの休息につながります。
2. 無言が「不安」ではなく「安心」になる関係性
沈黙がつらいと感じるのは、相手との関係がまだできていないとき。
逆に、信頼関係ができていると、無言の時間も“共にいる感覚”として温かく感じられるようになります。
訪問看護では、「無理に話させない」「言葉にならない気持ちも尊重する」関わりを大切にしながら、
“沈黙が安心に変わる瞬間”を見守っています。
訪問看護師が沈黙の時間にしていること
沈黙の中でも、看護師は多くのことを感じ取り、支援しています。
- 表情やしぐさの小さな変化
- 部屋の様子や生活環境の観察
- 呼吸や姿勢の違和感
- 「話せないことがあるのかも」という気づき
沈黙=何もしていない時間、ではありません。
看護師は、ことば以外のメッセージを受け取るために、全身で“聴いて”いるのです。
「話したくなったら、話せばいい」
訪問の中で、沈黙のあとにポツリと出る一言には、
深い思いや、抑えていた感情がこもっていることがあります。
たとえば…
- 「実は最近、夜が怖くて眠れなくて…」
- 「誰にも言ってなかったけど、少し落ち込んでいて」
- 「何をどう話していいか分からなかったんです」
こうした言葉が自然に出てくるのは、安心と信頼があってこそ生まれるもの。
私たちは、そのタイミングを焦らず待ち、
“言葉にできた瞬間”を大切に受け止めます。
沈黙も、心と心をつなぐ手段のひとつ
訪問看護では、「話さなければ」「聞き出さなければ」といった焦りを持たずに、
その人のペースに合わせた関わりを心がけています。
沈黙は、気まずさではなく、信頼と安心の証になることもある。
話さなくてもいい時間があることが、
“私は私のままでいていい”という感覚につながることもあります。
言葉が出なくても、沈黙でも、私たちはそばにいます。
haru style は、ことばにならない思いも大切に受け止め、
その人らしい時間を一緒に過ごしていきます。
どんな時でも、安心できる関係づくりを、これからも大切にしてまいります。
![精神科看護特化型 訪問看護ステーション haru style [ハル スタイル]|茨城県土浦市、かすみがうら市、つくば市、牛久市、阿見町、石岡市、竜ケ崎市](https://haru-style.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-haru_logo.png)